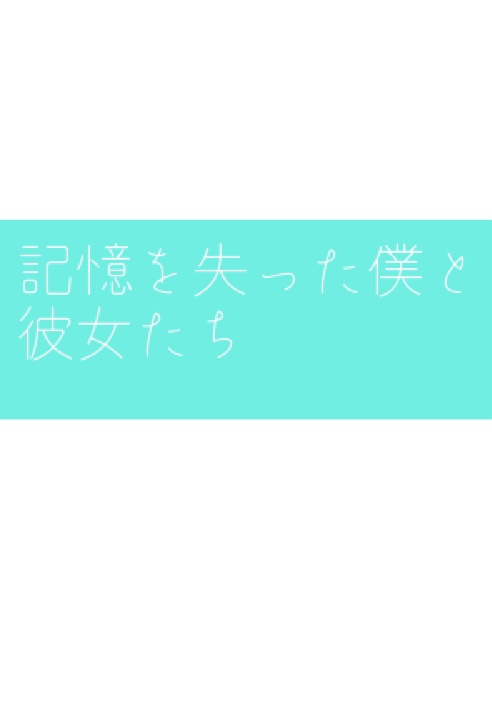
目覚め
眩しい。ここはどこだ?白い清潔感のある天井が見下ろしている。
愛斗は6日ぶりに目を覚ました。
「お兄ちゃん!?お母さん!お兄ちゃんが起きたよ!」
声は中学生くらいの女の子が何やら叫んでいる。
「お医者さんを呼んで!」
その子のお母さんだろうか。女の子に医師を呼ぶように告げた。その時、愛斗の顔の上を細く白い腕が通過した。そして、愛斗はここが病院であると初めて知った。
「どうされました?」
女の子の手によってナースコールが使用され、落ち着いたナースの声がスピーカーから発される。
「お兄ちゃ...愛斗くんが目を覚ましました!」
自分のことが言われているのだと察した。だが愛斗という名前は聞き覚えがない。
「愛斗!お母さんだよ?分かる?」
お母さんだと言い張る40代くらいの女性に分かる?などと言われても分からないものは分かるわけがない。とりあえず黙って動かないようにしよう。
部屋の外から2人分の足音が聞こえてきて、その足音の主たちは扉を開け愛斗の病室に入ってきた。片方は白髪混じりで50代くらいの男性の医師、もう片方は若めの女性のナース。どちらも愛斗のベッドの横に立ち、男性の医師は「音聴きますね」というようなことを愛斗に言って、聴診器で心臓の音を聴き始めた。その後も色々と身体を調べられ、やっと医師が口を開く。
「身体に問題はなさそうです。様子を見てですが2週間以内には退院出来ると思いますよ」
「そうですか。本当にありがとうございました。」
勝手に話を進めるな。僕は何が何だか分かってない。なんで入院しているんだ。この人たちは誰なんだ。そして何より僕は、誰だ?
「すみません、何で僕はここにいるんですか?」
「そうだね、分からないよね。君、愛斗くんは事故にあったとき、彼女さんを庇って頭を打って意識を失ったんだ。」
僕が聞きたいことはそういうことじゃない。確かに今の質問は言葉足らずだった。けど知らない人たちに囲まれている僕の気持ちになったら答えるべきは明白だろう。自分たちが誰なのか、僕は誰なのか…。あれ、知ってる人って誰だ?
愛斗は気づいた。知らない人しかいない。知っている人など誰もいないことに。ましてや自分のことも知らないのに知っている人がいる訳ない、と。
「あなたがたは誰ですか?そして僕は、誰なんでしょうか」
愛斗は分かった。部屋の空気が凍りついたことを。まるで時間が止まったかのような沈黙が続いた。部屋の中で動いているのはデジタル時計の文字盤だけ。他に動くものはなかった。
だが、その沈黙を破る者がいた。
「愛斗!目、覚めたんだね、よかった...」
1人の女性が目に涙を溜めながら病室に入ってきた。その女性は愛斗に近づき、愛斗の右手を両手で包み込む。愛斗はドキッとしたがその感情も長くは続かなかった。
「今西さん...。お話があります。一旦外にお願いします」
そう言われて今西という制服を着た女性は医師に連れられ部屋の外へ出て行ったからだ。
さっきから何が何だか分からない。女の子にお兄ちゃんと呼ばれ、女性にお母さんだと言われ、挙句の果てに知らない女性に手を握られた。
愛斗は考えることをやめ、再び眠りについた。夢なのか現実なのか、寝ぼけていて分からなかったが「お兄ちゃん、もしかして記憶が...」という声が耳に入ってきたような気がした。
眠りから覚め、視線を上げるとさっきの男性の医師が立っていて、その医師を見上げたついでに時計を見ると17時59分を示していて、沈黙のあの瞬間からは30分しか経っていなかった。自分をお兄ちゃんと呼んでいた女の子、つまり妹と思われる子と自分のお母さんと言っていた女性は部屋の中にはいない。帰ったのだろうか。
愛斗は視線を医師に戻す。
「僕は、記憶がないんですね?」
単刀直入に医師に尋ねた。
「自分の名前、生年月日、家族構成は言えるかな?」
「愛斗...しか分かりません。それもさっき聞いたから分かっただけで」
散々「愛斗」と呼ばれていれば、さすがに何も分からなくても自分の名前なのだろうと察することはできる。
「そうか...記憶喪失の可能性が高い。明日検査を受けてみようか。」
検査など受ける必要もない。僕自身が僕自身を記憶喪失だと認めているから。
だが、愛斗は素直に「はい」と返事をした。
「自己紹介がまだだったね。私は君の担当医師の須崎だ。何かあったら気軽に声をかけてくれ」
須崎という名の担当医師は優しく愛斗に微笑んだ。もしかしたらこの人といれば記憶を戻してくれるかもしれないという信頼感さえ湧く。
「私はあくまでも外科医だ。事故の手当てまでが私の担当だった。だけど君に全力で寄り添っていくつもりだよ。愛斗くんがいいと言ってくれるなら」
「もちろん、お願いします」
愛斗と須崎の間に信頼関係が生まれた。須崎は右手を愛斗の前に出す。愛斗はその手を握り返した。
「もう眠れないか?身体が大丈夫なら散歩してみるか?」
須崎が愛斗に散歩を勧める。
ずっと寝ていたのだろうし、気分転換にもいいかもしれないなと思い、愛斗は床に足をつけ、ゆっくりと立ち上がった。上手く脚に力が入らない。ベッドの手すりに掴まってやっと立てるという状態だ。
「車椅子持ってきてもらおう。ちょっと座って待っててくれ」
と須崎は言い、ナースコールで車椅子を持ってくるよう指示する。間もなく車椅子を持ったさっきのナースが部屋に入ってきて「どうぞ」と言い愛斗を介護しながら車椅子に座らせた。
「この病院は広いんだ。色々な物があるから何か思い出せるかもしれないな」
須崎は言った。
愛斗はそれが冗談半分だと分かっていても何かを少しでも思い出したいと切望していた。もしかしたら覚えているものがあるかもしれないという僅かばかりの希望とともに、須崎に押され車椅子の愛斗は病室を出て行った。
0 comments
Be the first to comment!
This post is waiting for your feedback.
Share your thoughts and join the conversation.
