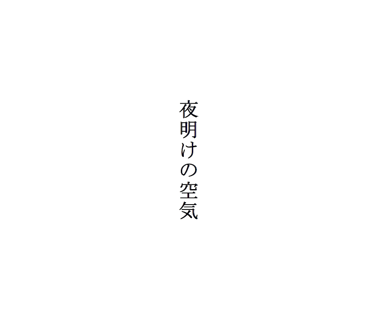
湿った呼び鈴が鳴って
猫がやってくる時間
ぼくは心臓の使い方をようやく思い出す
血液が太い管から細い管へと流れ込んで
繋がっている細胞の一つ一つに酸素とか栄養
を送り届ける
温度が上がっていく
蒸発した海のように
爆発した太陽のように
干からびた体は周囲の熱を奪っていく
猫はふわふわの体毛で
空気の上を歩く
音もなく歩く
水飲み場まで案内してくれる訳でもなく
ただぼくの顔を覗きに歩いてくる
その程度の繋がりが
生と死の揺れ続ける境界線なのかもしれない
ぼくは水が飲みたかった
猫は抱いて欲しそうだった
ずっと雨が降りそうだったのに
雨はずっと降らなかった
唾液を失った口にできることは
言葉を飲み込むことだけだった
舌先に触れる空気の滑らかさ
透明な血が流れている感覚の先に
枯れることのない泉が広がっている
言葉は永遠に消化できない
ぼくはどうしても祈りを思い出せずにいた
もう一匹の猫が呼び鈴を鳴らす
湿った夜がもうすぐ明ける
孤独の中に溶けていくように
それらは液体となってぼくの舌の上に落ちる
痺れるような感覚も
泣きそうになるほどの情熱も
波紋となって
空気がほんの少しだけ揺れる
0 comments
Be the first to comment!
This post is waiting for your feedback.
Share your thoughts and join the conversation.
